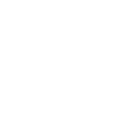遺品整理はいつから始めるべき?タイミングや行う時のポイントを解説

身近な方が亡くなった場合、遺品整理を行う必要があります。しかし、どのタイミングで作業を始めれば良いかわからず、悩まれる方もいるでしょう。そこでこの記事では、遺品整理をいつから始めるべきかについて解説します。作業を行う時のポイントもあわせて解説するので、最後までご覧ください。
この記事を読むための時間:3分
遺品整理はいつから始めるべきか
遺品整理を始める時期は、以下のようなタイミングがあります。
- 葬儀後
- 社会保険や役所などの手続き後
- 四十九日法要後
- 相続放棄の期限前
- 相続税の申告期限前
- 気持ちが落ち着いてから
葬儀後
葬儀が終わった直後は、気持ちの整理がまだつかない時期です。しかし、親族や関係者が集まるタイミングでもあるため、形見分けや今後の整理について話し合う機会として適切です。無理に進める必要はありませんが、今後のスケジュールを共有する意味でも、話し合っておくと良いでしょう。
社会保険や役所などの手続き後
公的な手続きが一段落すると、心に余裕が生まれる場合もあるでしょう。健康保険・年金・運転免許証などの返納手続き、銀行口座の名義変更などを済ませた後で、遺品整理に取りかかる方も少なくありません。書類関係が整理されていれば、遺品の中に大事な書類が紛れていた場合にもすぐに対応できます。
四十九日法要後
四十九日法要を区切りとして遺品整理を始める方も多いです。心の整理がつきやすい節目のため、親族と一緒に遺品を見直すタイミングとして適しています。
相続放棄の期限前
相続放棄を考えている場合は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。遺品整理を始めると、債務の有無や財産の状況が明らかになるため、判断材料になりやすいです。ただし、遺品の処分や使用が「相続を承認した」とみなされる場合もあるため、慎重に進めましょう。
相続税の申告期限前
相続税の申告は、相続開始から10カ月以内に行う必要があります。遺品に含まれる貴金属・美術品・不動産に関する書類などは、申告に必要な資料です。そのため、申告期限前にある程度の整理を終えておくと、スムーズに手続きを進めやすくなります。
気持ちが落ち着いてから
何より大切なのは、気持ちが落ち着いたタイミングで取りかかることです。無理をして早く進めようとすると、かえって心の負担になることもあります。少しずつ整理していくことで、大切な思い出を丁寧に振り返る時間にもなるでしょう。
遺品整理を行う時のポイント
遺品整理を行う時のポイントは、以下の5つです。
- 必要な手続きの内容を把握しておく
- 作業は計画的に進める
- 遺品をわかりやすく分類する
- 迷うものは一度保留にする
- 親族や業者とのトラブルに注意する
必要な手続きの内容を把握しておく
遺品整理を始める前に、まず相続や名義変更に関わる手続きの全体像を把握することが重要です。銀行口座の解約・保険金の請求・不動産の名義変更など、手続きを進めるには必要な書類や期限があります。あらかじめ役所や専門家に相談し、必要な手続きを一覧にまとめておきましょう。
作業は計画的に進める
遺品整理は想像以上に時間と労力がかかる作業です。感情的な負担も加わるため、無理をせずに進めましょう。部屋ごとに日程を区切ったり、複数人で分担したりすると効率的に進みます。また、故人との思い出に触れると気持ちが不安定になることもあるため、心に余裕を持てるタイミングを選びましょう。
遺品をわかりやすく分類する
作業をスムーズに進めるには、遺品を「残すもの」「処分するもの」「迷うもの」「譲渡するもの」などに分類するのがおすすめです。重要書類や貴重品などは別にして、紛失や誤処分を防ぎましょう。
迷うものは一度保留にする
遺品の中には、処分すべきか判断できないものもあります。そのような場合は「保留」の箱を用意して一時的に分けておくと良いでしょう。無理に判断しようとせず、時間を置いてから見直すことで冷静な判断がしやすくなります。
親族や業者とのトラブルに注意する
遺品整理は、相続人同士や業者とのトラブルが起きやすい作業でもあります。勝手に物を処分したり、価値のあるものを無断で持ち出したりすると、揉め事につながるおそれがあるため注意が必要です。また、業者を利用する場合は、信頼できる会社かどうかを事前に確認し、契約内容もしっかり確認しましょう。
適切なタイミングで遺品整理を行おう
遺品整理は感情や人間関係の問題も伴いやすいため、冷静かつ計画的に進めることが求められます。自分たちに適したタイミングを見極めると、無理なく作業を進められるでしょう。必要に応じて、専門家や業者のサポートも活用してみてください。