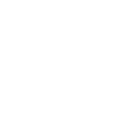代々農家に嫁ぎ、お米を作っています!今年も種蒔きの準備が始まりました。
私はお米を作る農家に嫁いで31年になり、代々引き継ぎ100年以上になります。
ご先祖の方々に感謝するばかりです。粘土質の環境で育ったお米をいつも低農薬で美味くいただき、出荷もしております。
日本でお米は大切な食料としての主役ですね。
米粉を使ったパスタ商品もあり、私も興味が湧いて通販で探して購入、驚きと共にいただきました!
食感はもちもちしていて美味しいです。
米粉を使ったお菓子、ブラウニーなども美味しそうでお菓子作りに挑戦し、米粉の特徴や食感に感激を覚えました!
お米、想像以上に魅力的です!



私の家でのお米栽培についてお話しさせていただきます。

お米作りの初めとなる種蒔き前の事前準備にはとても注意が必要で、私が住む千葉県大網白里市ではこの準備時期は寒暖差もあります。
ですのでお米の種蒔きを何日に行うか、種蒔きをする種籾をいつから初期処理するか、天気予報の情報をこまめに確認して進めています。
私が嫁いでから作った品種は、コシヒカリ、ふさおとめ、ふさこがねです。
それ以前は、ササニシキ、豊作早稲も作り収穫していたそうです。
今となっては機械を使うことが主流ですが、昔は手作業のみだった実話を聞き、長年先祖代々の方々が引き継いできた歴史を感じ、感謝、尊敬と感慨深くなるばかりです。
私が知る頃から作っていた品種はコシヒカリとふさおとめの2種類を栽培し、今年は収穫時期が早い早稲(わせ)ふさおとめ1種類を育てる段取りで進めてきました。
種蒔きは人手が確保できる3月16日、予報では残念ですが曇りと雨予報です。
逆算して、種籾を消毒液に浸ける日を2月28日とし、


以降は適したタイミングで浸ける水の入れ替えをしました。
これは、種籾のお目覚め前の環境作りです。
次は、種籾さんお目覚め開始です!
温かいお湯に入れてあげて、発芽準備です。
種籾の状態を見て、もう少し浸けておくか、出して水切りをして乾かすか判断していきます。

3月13日、種籾さんが発芽準備を始めてくれましたので乾かします。


この時以降、乾燥し過ぎは禁物ですので、ここでもこまめな確認と対応をしていき、種蒔きに備えます。
種蒔き機を動かして不具合がないかなどの確認は済んでいるので安心です。
あとは種蒔きの時に、土や種籾が入っても調子良く動いてほしいと願うばかり。
いよいよ種蒔きです。
天候は予報が変わることはなく起床時は雨、種蒔きの準備の際もシトシトと雨が降っていましたので、種蒔き場所からビニールハウスにかけてはシートを張り、屋根を作りました。

気温が低いので風邪を引いたり体調を崩さないように、そして整理片付け業務同様に作業効率と必要時間の短縮を考慮したものです。
種蒔き機は、種籾や土の量を一定にするため垂直になるよう設置し、電源を入れて動かし、まずは種籾の排出量を適切な量になるよう微調整。
これはベテラン様に習い、習得中です。
次は、土の排出量の確認し多すぎず少なくないよう調整し、水の量も確認します。
水も多すぎず少なくないよう、土の湿り具合いと表示を参考に決めます。

ひと通りの設定ができましたら、「さあ、動かすよ。」の声がけで所定の位置に構え、皆心構え。
育苗トレーを次々にセット!
始まるや否や、思いもよらないことが…
いざ動き出した途端に、余分な土を払うブラシの固定が若干緩かったようで、1枚目は土がてんこ盛りになり、即座にブラシの固定部を締め、2枚目からは順調に動いてくれて、種の蒔き具合いも土の量・水の量がちょうど良く進みました。
種蒔きが済んだ育苗トレーは、ハウスに置き保温開始となります。
保温のためのシートを掛け、翌日からは水分の湿り具合いを見て必要に応じて水やりをします。

その後背が伸びてきたので、保温シートを外す理想のタイミングはいつか、考慮が必要になりますが、明日からの数日はまた最高気温が低くなります。
苗は細く育つより太く育ってほしいので、気温や天気をみながら水やりやシートを外したり掛けたり対応していきます。
無事に発芽してくれて、ここまで成長しました!


そして現在はここまで成長しました。


もう少し伸びたら田植えです!このまま順調に成長してくれるように見守り、対応しながら育てていきます。
毎年、種蒔きでは全ての種籾が蒔き終わるまではヒヤヒヤ、田植えができる苗になるまで心配しながらですが、今年も家族やシャルネスタッフのおかげで無事に蒔き終わり、順調な生育に至っています。
次は、田植えのご報告ができるよう、お水をあげながら成長を見届けていきます。
シャルネ 齊藤 智世